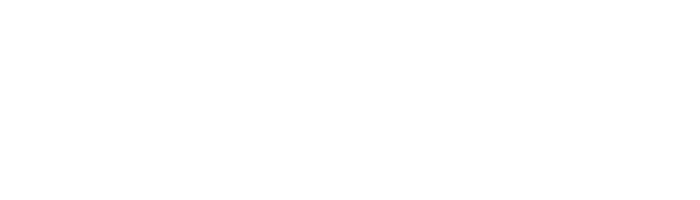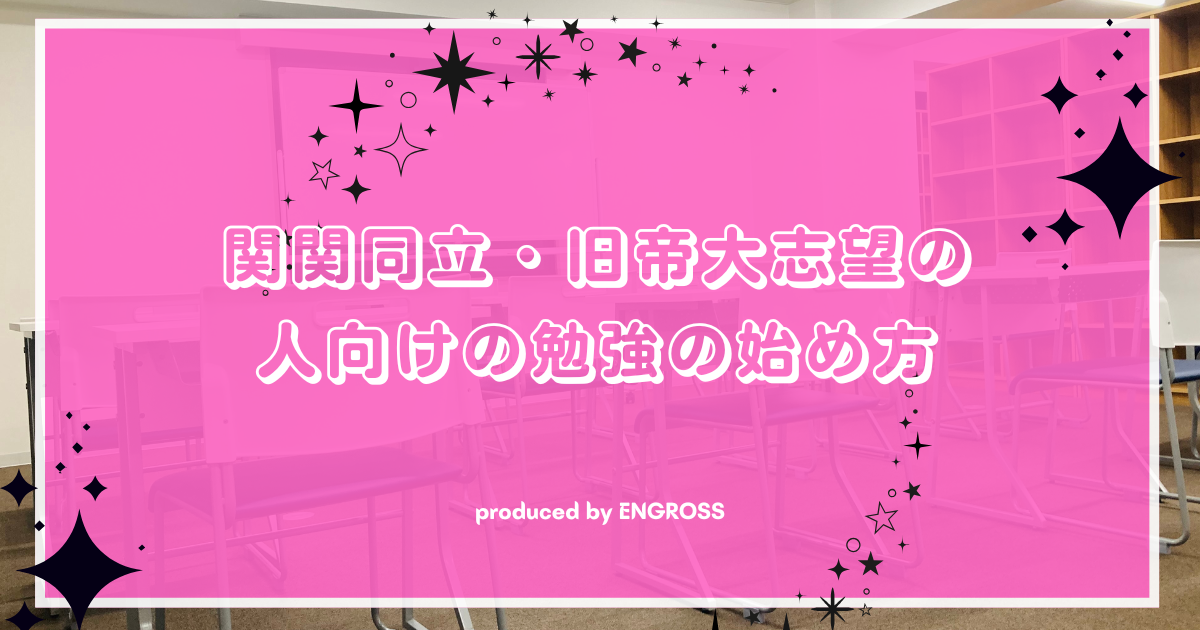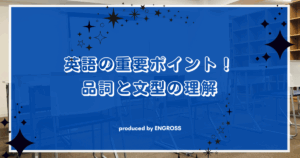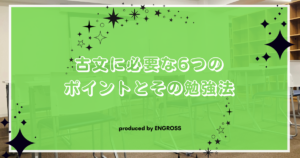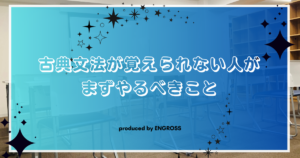「関関同立」や「旧帝大」って、聞いたことはあるけど、
実際にどんな勉強をすれば合格できるのか、イメージできていますか?
「とりあえず学校の勉強を頑張ればいいかな」
「予備校に行かないとムリかも…」
そんなふうに、なんとなく不安を感じている高校生も多いはずです。
でも実は、関関同立や旧帝大に合格している人たちには、ある共通点があります。
それは、“早い段階で正しい勉強法を知り、それを実行している”こと。
今回は、「今から始められる」+「成果につながる」勉強の始め方をお伝えします。
難関大を目指している人、まだ志望校が決まっていないけどレベルの高い大学に興味がある人はしっかり確認していきましょう。
難関大合格の鍵は「基礎力の徹底」
難関大学の入試問題というと、難解で複雑な応用問題ばかりをイメージされる方も多いかもしれません。
しかし、実際には「基礎力の有無」が合否を大きく左右します。
たとえば英語であれば、長文を読むにも文法を理解するにも、まずは単語力が必要です。
数学であれば、公式の理解や基本的な解き方が身についていないと、応用問題に太刀打ちすることはできません。
古文でも、単語や文法(助動詞・助詞など)の知識が前提になります。
つまり、難関大を目指すからこそ、早い段階で基礎を徹底しておくことが重要です。
基礎力がしっかりしていることで、どの教科も伸びしろが大きくなり、受験後半で一気に得点力が上がるケースも珍しくありません。
実は基礎力だけで解ける問題は多い
基礎が大事と言われても、難関大は難しい問題も出題されると思うでしょう。でも実際は意外と基礎問題が出題されています。例えば以下の問題を見てみましょう。
Sometimes I feel embarrassed telling you stuff like that because it just seems stupid. To be honest, I still look up to you a lot. I don’t want you to think of me as, I don’t know, out of my mind.
Q.下線部の意味に最も近いものはどれ?
・follow
・observe
・respect
・trust
・confuse
これは2022年の神戸大の問題から一部抜粋したものです。もちろん長文を読まないといけないのですが、この問題だけ見れば、「look up to〜」が尊敬するという意味だと気づけばすぐに「respect」が答えだとわかります。普通に勉強している人からすれば、簡単な問題でしょう。
もちろん、このレベルの問題だけが出題されているわけではないですが、それでも基礎レベルを知っているだけで解ける問題も多々あります。それを確実に解けるようにすることは難関大突破の一番大事な部分になります。
焦って応用問題に取りかかるのではなく、「わかる」を「できる」に変えること。
この地道な積み重ねが、難関大学合格のための一番の近道です。
早めに「過去問を見ておく」
過去問は「受験直前に取り組むもの」と思われがちですが、早めに過去問を見ておくと良いです。特に志望校が明確になっている子はできれば高校1〜2年生のうちから過去問に触れておきたいです。
もちろん、この段階ではまだすべてを解ける必要はありません。
それでも、出題の形式や傾向を知ることが、日々の学習の質を大きく高めてくれます。
なぜ、早いうちから過去問を見ておくべきなのか?
ただ、過去問は別に直前で良いのでは?と思うかもしれません。ただ、過去問を早めに見ておくと以下のメリットがあります。
- 「どんな問題が出るか」を知ると、今の勉強の目的が明確になる
- モチベーションアップにつながる
- “逆算型”の勉強ができるようになる
英語の長文問題が中心なら、語彙力や速読力を意識して単語や構文を覚える必要があります。古文で現代語訳の問題が多く出るなら、その練習をしていく必要があります。
また、実際の問題を目にすると「自分もここを目指すんだ」という意識が高まり、日々の勉強に張りが出ます。
加えて、志望校のレベル感を把握することで、「今やるべきこと」「いつまでに仕上げるべきか」が逆算しやすくなります。
早めに見たときにはできない問題が多い、こんな難しい問題が出るのかと考えてしまいますが、そのタイミングでできるできないは気にしなくて良いので、まずはどんな問題が出るのかを意識しておきましょう。
志望校が決まっていない場合やまだ全単元が終わっていない場合
実際には志望校が決まっていないかったり、そのタイミングでは進度的に半分も進んでいないということもあるかと思います。その場合は、受ける可能性がある大学の問題やそこまでの進度で解ける問題だけでもよいので目を通してみましょう。
最初は問題を解こうとせず、ざっと目を通すだけでもOKです。過去問は「志望校との距離」を知るための大切な地図のようなものです。早いうちから触れておくことで、自分にとって必要な勉強がより明確になっていきます。出題傾向や形式を把握して、どの教科にどんな対策が必要かを考えるようにしましょう。
「自分の弱点」を早めに把握し、対策する
難関大学を目指すうえで、得意科目を伸ばすことはもちろん大切ですが、それ以上に重要なのが弱点を放置しないことです。どんなに点数を稼げる科目があっても、苦手な科目で大きく失点してしまうと、合格は一気に遠のいてしまいます。
弱点の早期発見がカギになる理由
- 受験直前の追い込みでは、苦手を一気に克服するのは難しい
- 「できない理由」を明確にしておけば、対策の方向性が見える
- 苦手なままにしておくと、勉強そのものへの自信を失いやすい
特に英語や数学は、積み上げが必要な科目です。時間をかけた対策が不可欠です。苦手克服には時間もかかり、また根本原因を探る必要もあります。例えば「英語の長文が苦手」というケースがあります。ただ、実際は単語力が不足していたり、文構造が読めていなかったりするのが根本の原因であるというケースが多いです。
「数学の図形が苦手」というケースでは定理の理解不足や問題演習が足りないケースもあります。できないのがなぜなのかを追求することで、対策が見えてきます。
そして苦手科目が足を引っぱると、勉強全体のやる気が下がるケースもあります。
弱点の見つけ方と対策のポイント
弱点克服には何をすれば良いでしょうか。一番大事なことは普段の勉強をしっかりやることです。特に模試や定期テストの復習を大切にしましょう。「どこを間違えたか」だけでなく、「なぜ間違えたか」まで分析しましょう。また、参考書や問題集は、できなかった問題に印をつけて繰り返していきましょう。よく「問題集を⚪︎周すれば良い」というアドバイスがありますが、より大事なのはその中で何ができて、何ができないか把握していくことです。そしてできない問題をできるように変えていくことが大事です。回数ではなく、その中でできないものをなくしていく意識を持ちましょう。
その中で何か困った場合には先生や塾に相談するのもおすすめです。自分一人では見えにくい弱点も、第三者の目で気づけることがあります。
苦手な部分を早く見つけて、対策を始めること。それが合格への土台を築き、後半の伸びにつながります。
勉強習慣を作ることが最優先
どれだけ質の高い勉強法を知っていても、それを“継続”できなければ結果にはつながりません。
難関大合格のためにまず最初に取り組むべきなのは、勉強を習慣化することです。
「毎日続けること」がなぜ重要なのか?
なぜ毎日続けるのが大事なのでしょうか。それには3つ理由があります。ひとつは知識は一度覚えても、使わなければすぐに忘れてしまうからです。一回覚えたと思っても気づいたら忘れてしまいます。それをなくすにはこまめに復習する習慣が大事です。復習で繰り返すことで記憶の定着につながります。
2つ目に習慣化して毎日勉強を積み重ねていくと自然と自信もついてきます。「今日は昨日よりもできた」と感じる経験がモチベーションの原動力になります。加えて、毎日続けたことで受験前に焦らなくてすみます。受験前になるとどうしても焦りが出てきます。でもコツコツ進めることで、最後の時期には仕上げに集中できるようになります。
書いてしまえば簡単ですが、これを継続するのが大変です。うまくルーティン化してコツコツ進めていきましょう。
習慣化のための工夫
それでは勉強を習慣化するにはどうすればいいでしょうか。まずは短時間でもいいので「毎日同じ時間に勉強する」ことから始めてみましょう。たとえば「夕食後の30分だけ英単語」といったルールを決めると継続しやすくなります。
また、どうしても続かない人は勉強の内容を記録するのもおすすめです。「今日は何をやったか」を記録しておくと、進歩が可視化され、やる気アップにつながります。モチベーションが続かないという人は試してみましょう。
また最初から完璧を求めすぎないのも大事です。いきなり完璧なものを求めると身体的にも精神的にも苦しく、継続が難しくなります。1日休んでも「翌日取り戻せばいい」と柔軟に考えることで、長続きしやすくなります。
勉強習慣は、最初のうちは意識的に「作る」必要がありますが、習慣が定着すれば大きな武器になります。塾なども活用してコツコツと勉強していきましょう。
受験は「戦略」がすべて
とはいえ難関大学への合格を勝ち取るには、とにかく頑張るだけでは足りません。
大切なのは、「合格から逆算して、何をいつまでに仕上げるか」を考えることです。つまり、戦略的に取り組む姿勢です。
戦略的な勉強が必要な理由
入試には明確な「出題傾向」と「配点の重点」があります。この大学ではこの問題でやすいとか、この大学は毎年この形式が出ているとか、この学部は英語の配点が非常に高かったり、記述式の対策が必要だったりなど、大学によって傾向はさまざまです。そうなると限られた時間の中で、優先順位をつけることも重要になってきます。
また、模試や過去問を通じて、常に戦略を見直す柔軟さも求められます。成績の伸び方や、受験直前の課題に応じて戦略はアップデートする必要があります。
受験戦略を立てるポイント
それでは受験戦略はどんな形で立てれば良いでしょうか。ポイントをまとめると以下となります
・志望校の出題傾向を分析する(配点・問題形式・頻出テーマなど)
・自分の得意・不得意を整理し、時間の使い方を工夫する
・月ごと・週ごとに「目標とスケジュール」を立てて管理する
まずは赤本や公式サイトの情報を活用しましょう。どんな形式が出ているかを確認して、何をすべきかを考えましょう。繰り返しにはなりますが、そのために、早めに過去問をみておくことが大事になります。また、時間の使い方も大事です。空いている時間の使い方や、たとえば「朝の通学時間帯は英単語、夜家に帰ったらまずは数学」といった時間帯別の戦略も効果的です。小さな目標の積み重ねが、大きな自信へとつながるので、うまく時間を使っていきましょう。
受験は長期戦です。その中で、「今の自分に必要なことは何か」を見極めながら進むことが合格への確かな道となります。
難関大合格へのスタートは「今この瞬間」から
難関大学の合格を勝ち取るためには、特別な才能や一夜漬けの勉強ではなく、
「正しい方向性でコツコツ積み重ねる力」が何よりも大切です。
- まずは勉強習慣を身につけること
- そして自分の弱点を早めに知って、対策を打つこと
- 最後に戦略的に受験を捉え、必要なことに集中すること
この3つを意識して、今から一歩ずつ前に進んでいきましょう。
無料体験で、あなたの「今の学習スタイル」を見直してみませんか?
当塾では、関関同立や旧帝大を目指す高校生のために「勉強のやり方」から一緒に考える学習指導を行っています。
- 「今の勉強で合ってるのかな?」
- 「何から始めればいいのか分からない…」
そんな方こそ、ぜひ無料体験にお越しください。
一人ひとりの目標に合わせたアドバイスを行い、
合格への第一歩を一緒に踏み出せるよう全力でサポートいたします。